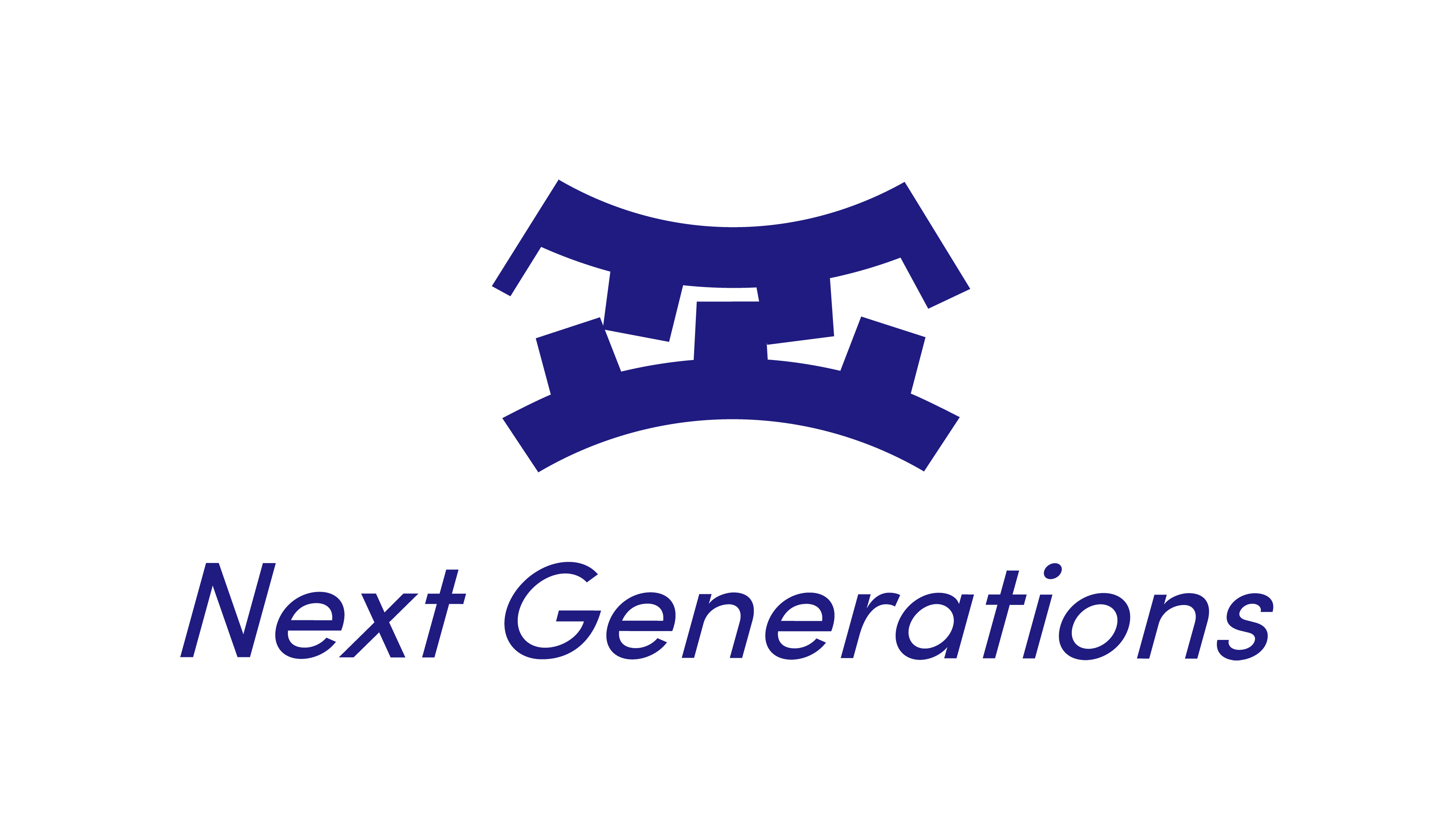ホンダ系ディーラーで新人研修を対応させていただきました。
2日間に渡りホンダ系ディラーの新人メカニックに研修をさせていただきました。
通常の研修会場は、学校法人小山学園様の教場で実施することが多いのですが、
今回はディーラー店舗にお伺いしての研修となりました。
内容は基本的な測定器の使用方法から新車6か月点検の内容になります。
今回は整備士資格を取得していない方を対象に研修を行いました。
参加された方々がとても熱心に受講されている様子がとても印象的でした。
今回の研修が終わると、店舗に配属される様です。
今後の活躍を期待しております。
研修メニュー(抜粋)
・安全作業
・ノギスの使い方と実践
・ジャッキアップとタイヤローテーション
・エンジンルーム点検
・ブレーキ点検
・灯火類点検