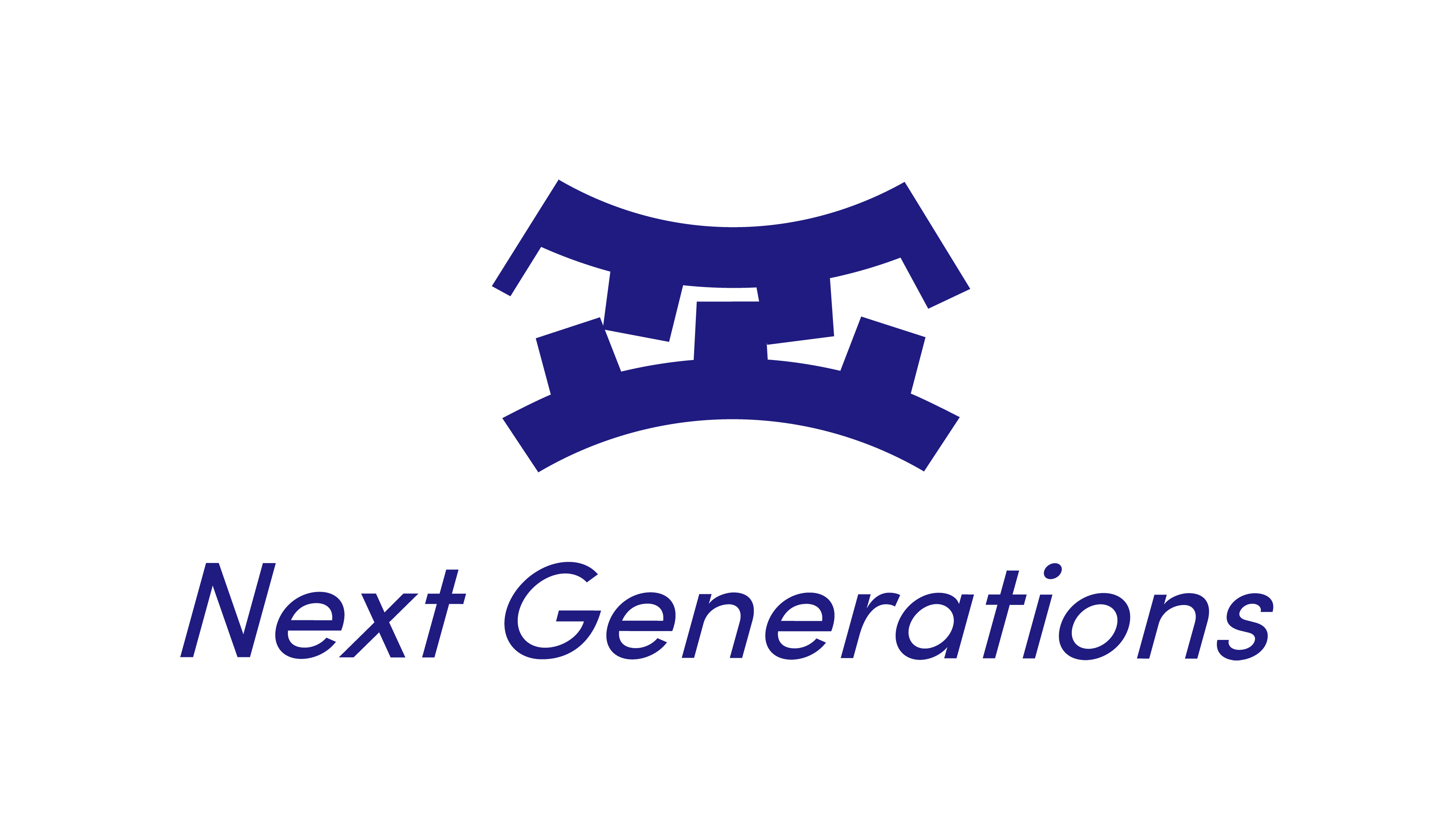令和6年3月1級〔問題1〕
〔No. 1〕 センサに関する記述として, 不適切なものは次のうちどれか。
(1) バキューム・センサ(圧カセンサ)は, 半導体チップ(シリコン・ チップ)にひずみを与えることで, 抵抗値が変化するピエゾ抵抗効果を利用したもので, 半導体チップに作用した圧力の大小による抵抗変化で圧力値を検出する。
(2) O2センサに用いられる円筒状のジルコニア素子は, 内外面に白金がコーティングされており,活性化領域(例:360℃)を超えたとき, 大気側と排気ガス側の酸素濃度差により, 起電力を発生させる性質がある。
(3) ノック・センサは, センサ・ ボデーに固定されている振動板に5V安定化電源を加えることで,振動板上の圧電素子に掛かる力(エンジン全般の振動成分)に応じた起電力を発生し, ノッキングによる振動を検出する。
(4) 測温抵抗体は, サーミスタと同じように温度によって抵抗値が変化する抵抗体で, サーミスタと比べ温度係数, 温度抵抗変化幅, リニア変化特性, 温度抵抗値精度などの温度検出精度に優れた特徴を備えている。
1級小型自動車整備士登録試験に出題された問題であるが、内容としては2、3級ガソリンの内容が多く含まれている。
(1) バキュームセンサについては3級総合p116にいくらかの言葉は違うものの、ほぼ同様の記載があることがわかる。
(2) O2センサについても同様に3級総合p120に記載がある。ここで触れられていないのは、活性領域の温度程度である。
(3) ノック・センサについては2級総合p291に記載がある。ノック・センサは圧電素子を用いたセンサであり、素子に圧力が加わり変形することで起電力を発生させるものであり、外部から、他のセンサの様に電源を加えるという仕様ではない。つまり、2級課程の内容を理解していることで、この文章は不適切であることが判断できる。
(4) 測温抵抗体については1級エンジン電制p83に記載があり、文面のままである。従来温度センサに採用されていたサーミスタと同様温度による抵抗変化が起きるが、多くの部分で優れている。
以上の解説から、自動車整備士の資格取得について、いかに3級、2級に関する理解が必要であるかが理解いただけると思う。